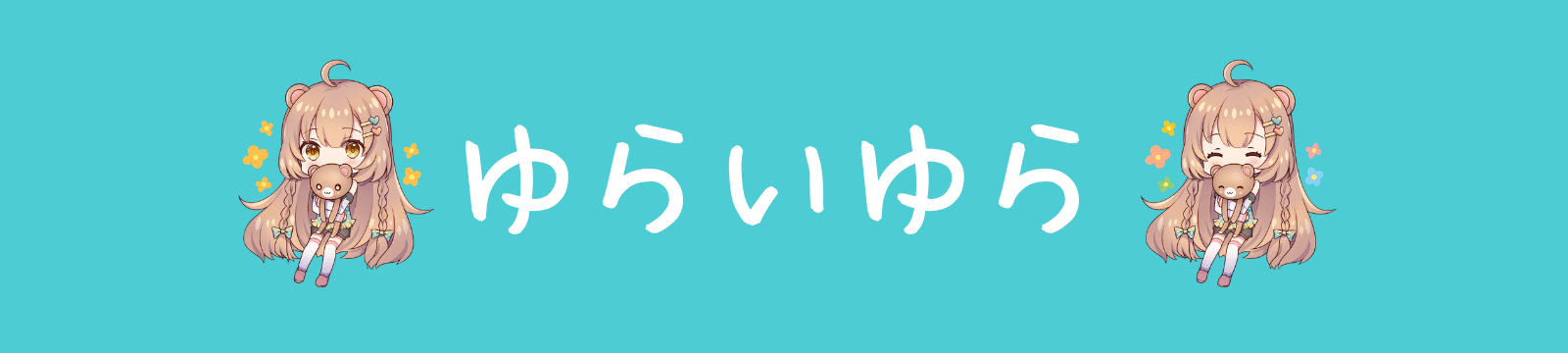宮城県塩竈市(しおがまし)の名前の由来・情報をまとめたページです
もくじ
宮城県塩竈市の名前の由来
- 「塩竈」 → 海水を煮て塩を採るための「竈(かまど)」を指す言葉
- この地には塩を造るための「塩竈」が数多く作られ、その場所が有名になったことから、そのまま地名になったとされている
- 現在も御釜神社で伝承される「藻塩焼神事」は、塩作りが古代から行われていたことを物語る神事
- 奈良時代に陸奥国の「国府の港」として栄えた「国府津(こうづ)」と呼ばれていた時期もあった
- しかし、陸奥国一之宮である鹽竈神社が信仰を集めるようになり、港町と地域名を「国府津」から「塩竈」へと変えていったとされている
宮城県塩竈市の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 市町村名 | 塩竈市 (しおがまし・Shiogama) |
| 面積 | 17.38 km² |
| 人口 | 49,884 人 (推計人口・2025年9月1日) |
| 人口密度 | 2,870 人/km2 |
| 地方 | 東北地方 (とうほくちほう) |
| 市町村の木 | シオガマザクラ |
| 市町村の花 | シラギク |
| 隣接自治体 | ・多賀城市 ・宮城郡利府町 ・七ヶ浜町 |
| 市町村公式ページ | 塩竈市公式ページ |
宮城県塩竈市の特産品・名物
- 三陸塩竈ひがしもの(マグロ)
日本有数の生マグロの水揚げ量を誇る塩竈を代表するブランドマグロ
9月から12月にかけて三陸沖で獲れる、鮮度と脂のりが最高のメバチマグロ - 水産練り製品(笹かまぼこなど)
塩竈市の水産練り製品は、日本有数の生産量を誇る
特に笹かまぼこは、宮城を代表するお土産として知られている - 牡蠣
- 竈さば(がまさば)
塩竈港で水揚げされた新鮮なサバを使った加工品
缶詰や生ハムなどが商品化されている - 志ほがま
塩竈の地名に由来する、落雁風の和菓子
蒸して乾燥させたもち米と、青じそを散らして作るのが特徴
宮城県塩竈市の観光地など
- 鹽竈神社(しおがまじんじゃ)
松島湾を見下ろす高台に鎮座する、東北地方の総鎮守、陸奥国一之宮
主祭神は海路の神・製塩の神である塩土老翁神(しおつちおぢのかみ)で、海上安全や安産祈願にご利益があるとされる - 志波彦神社(しわひこじんじゃ)
鹽竈神社と同じ境内に鎮座するもう一つの神社で、農業の神が祀られている - 御釜神社(おかまじんじゃ)
鹽竈神社の境外末社で、「日本三奇」の一つに数えられる「四口の神釜」がご神体として祀られている
釜の水の増減や色の変化によって、世の中に変事が起こると伝えられている - 浦霞醸造元(佐浦)
1724年創業の老舗酒蔵
鹽竈神社の御神酒(おみき)も醸造している - 塩釜水産物仲卸市場(しおがますいさんぶつなかおろししじょう)
生マグロの水揚げ量が日本有数の塩竈港にある、東北最大級の魚市場 - マリンゲート塩釜
松島や浦戸諸島への観光船の発着ターミナル
松島湾の美しい多島美を海の上から眺める遊覧船が運航 - 松島湾めぐり遊覧船
マリンゲート塩釜から出発し、日本三景の松島湾を巡るクルーズが楽しめる - 浦戸諸島
松島湾に浮かぶ、桂島・野々島・寒風沢島・朴島からなる、塩竈市の離島
マリンゲート塩釜から市営汽船で渡ることができる
宮城県塩竈市の祭りなど
- 塩竈みなと祭
日本三大船祭りの一つで、毎年「海の日」に開催される
戦後の水産業と地元の復興を願い、1948年に始まった - 帆手まつり(ほてまつり)
340年以上続く鹽竈神社の伝統行事
毎年3月10日に行われる防火を願う祭り - 御釜神社 釜神まつり
鹽竈神社の末社である御釜神社で、毎年7月上旬に開かれる祭り - 塩竈神社 花まつり
毎年4月第4日曜日に開催される、江戸時代を起源とする伝統的な祭り - 塩竈のひがしものフェア
塩竈を代表する生マグロ「三陸塩竈ひがしもの」の漁獲時期である、9月~12月ごろに開催されるイベント