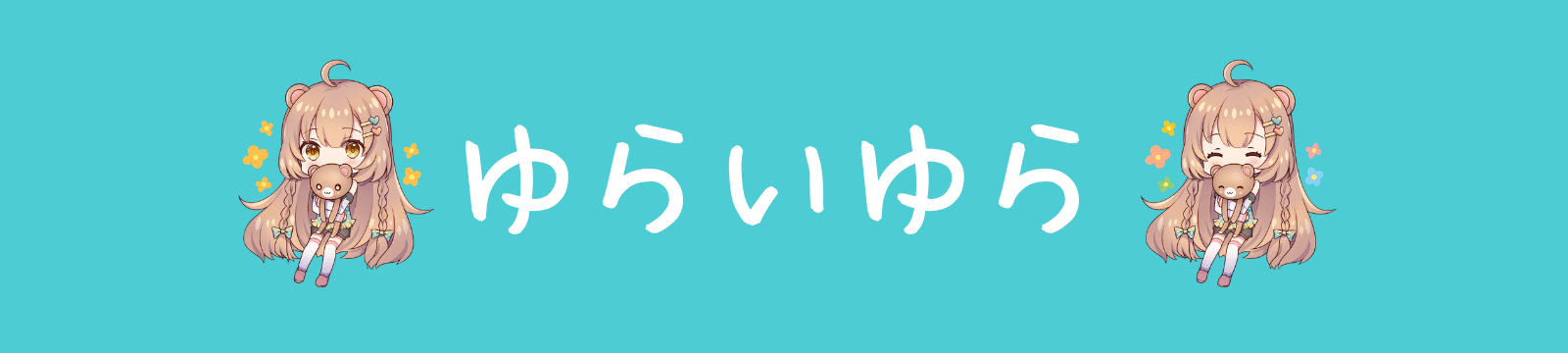「みかん」の名前の由来・雑学をまとめたページです
もくじ
みかんの名前の由来
- みかんの漢字表記は「蜜柑」
- これは「蜜のように甘い柑橘」の意味
- 中国から伝わった際、それまでの柑橘よりも甘かったことに由来している
みかんについて



みかんのあれこれを紹介していくよ
みかんの起源
- みかんの歴史は非常に古く、起源は中国南部の温暖な地域にある
- 気候と地形が柑橘類の栽培に非常に適していたため、主に中国南部の雲南省、広東省、福建省などの地域で古代から栽培されてきた
- これらの地域は、
・年間を通じて温暖な気候
・十分な降水量
・肥沃な土壌
などにより、柑橘類の成長に必要な条件を満たしていた - 当時中国でのみかんは、果物としてだけではなく、薬用や儀式用の重要な植物とされていた
- 古代中国の医療では、柑橘類の果実や皮が風邪の治療や消化促進に使われ、
皇帝や貴族の健康を守るために栽培が奨励されていた - 後にみかんは中国南部だけでなく、北部や中央部の地域にも広がり、中国全土で愛される果物となった
- シルクロード(東洋と西洋を結ぶ交易路)を通じて世界各地へ広まった
日本でのみかん
- 日本にみかんが伝わったのは、奈良時代(710年〜794年)とされている
- 最初に伝わったみかんは「唐橘(からたちばな)」と呼ばれ、薬用植物として扱われていた
- 現在の日本で一般的なみかんは「温州みかん(うんしゅうみかん)」
- 当時伝わったみかんは温州みかんとは異なる品種であり、
果実が小さく、やや苦みがあるものだった - また、「唐蜜柑(からみかん)」・「みっかん」と呼ばれていた時代もある
- 17世紀の辞書にも「miccan」と表記されており、江戸時代には「みっかん」の呼び方が一般的だった
- 時代と共に小さい「ッ」が省略され、明治時代以降に今の「みかん」の呼び方が一般的になった
- みかんが日本に伝わった奈良時代以降、徐々に国内で栽培されるようになった
- 平安時代(794年〜1185年)には貴族の庭園や寺院の庭で観賞用としても植えられた
- 一般庶民に広がったのは江戸時代(1603年〜1868年)
- 鹿児島県で現在の「温州みかん」が発見されたことがきっかけ
温州みかんについて
- 現在の日本で一般的なみかんである「温州みかん(うんしゅうみかん)」は、
江戸時代に、鹿児島県で発見された
(鹿児島県長島が原産地とされている) - 突然変異によって生まれた品種と考えられている
- 種がなく、皮が薄くてむきやすいという特徴がある
- また、日本の気候に適していたことから、全国各地で栽培が広がった
- 「温州(うんしゅう)」は、中国浙江省の地名
- 「温州みかん」は中国原産ではなくはないが、
かつて中国の温州地方で柑橘が名産とされていたため、この名前をつけた - 「温州みかん」は国外でも有名で、英語では「Satsuma」と呼ばれている
- 明治時代に薩摩(鹿児島県)から苗木が欧米へ送られたことに由来
- DNA研究によって、
温州みかんの親は、キシュウミカンとクネンボであることが判明している
みかんの代表的な品種
| 代表品種 | 主な産地 | 特徴など |
|---|---|---|
| 有田みかん | 和歌山県 (特に有田地方) | 全国最大の生産量 宮川早生を中心に早生や極早生品種も多数 |
| 宮川早生 | 和歌山県 愛媛県 など | 早生(早く収穫できる)品種 特に和歌山で多い |
| ゆら早生 | 和歌山県 | 和歌山のオリジナル極早生品種 糖度が高く「味一ゆら早生」としてブランド化 |
| 青島温州 | 静岡県 | 晩生(遅い収穫)で静岡の代表品種 糖度高くコクのある味わい |
| 寿太郎温州 | 静岡県 | 静岡発祥 青島温州より小ぶり 貯蔵がきき、熟成味の甘さが特徴 |
| 紅まどんな | 愛媛県 | 愛媛の高級ブランド 柔らかくゼリー状の果肉 濃厚な甘さ |
| 甘平 (かんぺい) | 愛媛県 | 大玉で平たい形 シャキッとした食感 しっかりした甘さが特徴 |
| 興津早生 | 和歌山県 静岡県 など | 早生品種 収穫時期が早い |
| 林温州 | 和歌山県 | 晩生品種 しっかりした味 保存性が良い |
みかんの主な生産地
みかんの雑学・豆知識



みかんの雑学あれこれを紹介するよ
「夏みかん」の名前の由来
- 冬に収穫し、保存して夏に食べごろとなるから「夏みかん」と呼ばれるようになった
- 夏に採れるからというわけではないのが面白い点
11月3日と12月3日は「みかんの日」
- 「いい(11)みか(3)ん」の語呂合わせ
- みかんが昔「みっかん」と呼ばれていたことから「3日(みっか)」ともかかっている
- 全国果実生産出荷安定協議会と農林水産省が制定
和歌山剥き(有田むき)
- 和歌山県で編み出された手を汚さずに最速でみかんを剥く方法
- みかんを皮ごと4分割してから剥くというユニークなテクニック
みかんの木の高さ
- みかんの種類にもよるが、一般的にはだいたい1.5~2mくらいの高さとなることが多い
みかんの花の色
- みかんの花の色は白色
- 3㎝くらいの小さな白い花を咲かせる
- 開花時期は5月頃
みかんがオレンジ色になる理由
- みかんの実は、はじめは緑色をしている
- そこから気温が下がることにより、緑色の色素が分解されていく
- この緑の色素と入れ替わりで黄色の色素が現れてくるため、
収穫の時期である冬頃には鮮やかなオレンジ色をしている
種のないみかんをどうやって増やしているのか
- 種のないみかんは「接ぎ木」で増やしている
- 「接ぎ木」→枝や芽を切り取って他の樹木にくっつけて増やしていく方法
みかんは日本で3番目に食べられている果物。1位と2位は?
- みかんは昔は日本で一番よく食べられていた果物
- 現在の日本人の果物消費量は、
1位…バナナ
2位…リンゴ
3位…ミカン
みかんを食べると手が黄色くなるのはなぜ?
- みかんには「β-カロテン」という栄養素が多く含まれている
- β-カロテンは黄色い色素で、
皮膚の表面にある角質に入り込みやすい - 手や足には角質が多いため、黄色くなりやすい
みかんを長持ちさせる保存方法は?
- ヘタの部分を下にして置くと良い
- みかんの水分はヘタから出ていく
- ヘタを下にすることで水分の出口を閉じ込め、
みかんが乾燥しにくくなり長持ちする
みかんを揉むと甘くなるのはなぜ?
- みかんは揉むと細胞が傷つく
- その細胞を治すのに使われているのが「クエン酸」
- 「クエン酸」は、みかんの酸味を作っている成分
- クエン酸が傷を治すのに使われて数が少なくなるため、
みかんの酸っぱさが減って甘さをより強く感じられるようになる
日本最古のみかんの木は大分県にある
- 大分県 津久見市 に、日本最古のみかんの木がある
- 品種は紀州みかんの木
- 樹齢850年以上とされる
みかんは冷凍すると甘くなる
- みかんの甘味成分は「果糖」
- 「果糖」は、冷やすと甘くなる性質がある
冷凍みかんが初めて販売されたのは駅の売店
- 1956(昭和31)年の夏、
東海道本線小田原駅の鉄道弘済会売店で、初めて冷凍みかんが販売された - 冷凍みかんは、マグロの冷凍技術を参考に開発された
みかんの缶詰が開発されたのは明治時代
- 1877年(明治10年)頃、海外への輸出を目的として、
みかんの缶詰が開発された - 開発当初は、ミカンの外皮がついたまま缶詰にしたものだった
- そのため全く人気が出なかった
- 昭和になると薄皮を一気に剥がす技術が開発され、
味も良くなり、大量生産もしやすくなった