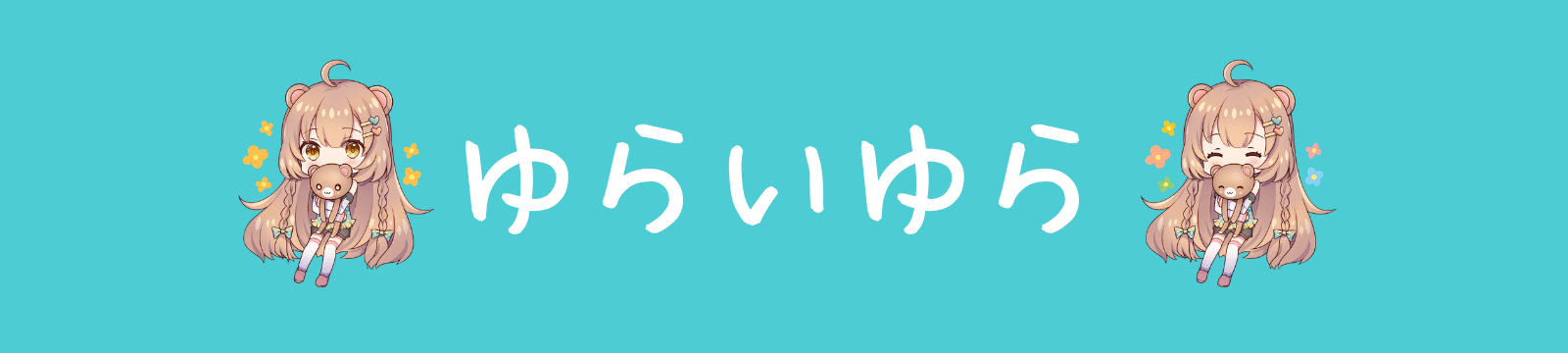今回は、経済の状態を表す「インフレ」と「デフレ」、そしてそれに関わる「マインド」についてです。
- インフレ(インフレーション)
- デフレ(デフレーション)
- インフレマインド
- デフレマインド

ニュースでよく聞く言葉だけど、実際にどういう意味なのか、わかりやすく解説するよ
もくじ
インフレとデフレの違い
- インフレ : モノやサービスの値段が継続的に上がり、お金の価値が下がる状態
- デフレ : モノやサービスの値段が継続的に下がり、お金の価値が上がる状態



くわしくみていこう!
インフレ(インフレーション)



まずはインフレについて!
インフレの具体例
具体例
- 去年100円で買えたりんごが、今年は110円になった
- 同じ給料でも、買えるモノの量が減る
- お金を持っているだけでは、実質的な価値が目減りする



ピンとこないときは、大きめな数字で考えてみるのもわかりやすいよ!
大きめな例
- 去年1,000円(一千円)で買えたりんごが、今年は10,000万円(一万円)になった
- 去年は千円札1枚=りんごが買える価値があったが、
- 今年は千円札1枚=りんごを買えないくらいの価値になってしまった
- →同じ給料でも、買えるモノの量が減る
- →お金を持っているだけでは、実質的な価値が目減りする
インフレの特徴
- モノの値段が上がる
- お金の価値が下がる
- 企業の売上が増えやすい(名目上)
- 給料も上がりやすい傾向
- 借金の実質的な負担が軽くなる
- 適度なインフレ(年2%程度)は経済成長に必要とする見方もある
デフレ(デフレーション)



次はデフレについて!
デフレの具体例
具体例
- 去年110円だったりんごが、今年は100円になった
- 同じ給料でも、より多くのモノが買える
- お金を持っていれば、実質的な価値が増える



ピンとこないときは、大きめ数字で考えてみるのもわかりやすいよ!
大きめな例
- 去年10,000円(一万円)で買ったりんごが、今年は1,000円(一千円)になった
- 去年は千円札1枚=りんごを買うことができないほどの価値しかなかったが、
- 今年は千円札1枚=りんごを買えるくらいの価値になった
- →同じ給料でも、買えるモノの量が増える
- お金を持っていれば、実質的な価値が増える
デフレの特徴
- モノの値段が下がる
- お金の価値が上がる
- 企業の売上が減少しやすい
- 給料も下がりやすい傾向
- 借金の実質的な負担が重くなる
- 長期的なデフレは経済停滞を招く可能性がある
インフレマインドとデフレマインドの違い
- インフレマインド : 「これから物価が上がる」という期待や心理状態
- デフレマインド : 「これから物価が下がる(もしくは上がらない)」という期待や心理状態



ここでいう「マインド」とは、人々の経済に対する心理状態や期待のことだね!
くわしくみていこう!
インフレマインド



まずはインフレマインドについて!
インフレマインドのときの人々の動き
- 「今買わないと、将来もっと高くなる」と考える
- 消費が活発になる
- 企業は値上げをしやすくなる
- 給料の引き上げを求めやすくなる
- お金を使ったり、投資したりする傾向が強まる
経済への影響
- 消費が増える → 企業の売上が増える
- 企業が儲かる → 給料が上がる
- 給料が上がる → さらに消費が増える
- 好循環が生まれやすい
デフレマインド



次はデフレマインドについて!
デフレマインドのときの人々の動き
- 「今買わなくても、将来もっと安くなる」と考える
- 消費を控える(買い控え)
- 企業は値上げをしにくくなる
- 給料の引き上げも期待しにくい
- お金を使わずに貯金する傾向が強まる
経済への影響
- 消費が減る → 企業の売上が減る
- 企業が儲からない → 給料が上がらない
- 給料が上がらない → さらに消費が減る
- 悪循環が生まれやすい
インフレとデフレ、マインドの関係まとめ



最後にまとめていくよ!
経済状態
- インフレ : 物価上昇・お金の価値が下がる
- デフレ : 物価下落・お金の価値が上がる
人々の心理(マインド)
- インフレマインド : 「物価が上がる」と期待 → 今買おう → 経済が活性化
- デフレマインド : 「物価が下がる」と期待 → 買い控え → 経済が停滞